 +86 18988945661
+86 18988945661 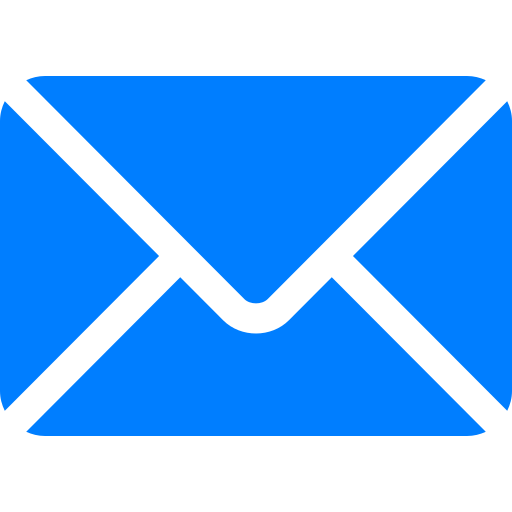 contact@iflowpower.com
contact@iflowpower.com  +86 18988945661
+86 18988945661
一般的な高電圧リチウムイオン電池の充電方法は何ですか?
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Leverancier van draagbare energiecentrales
高電圧リチウムイオン電池とは何ですか? 人生の中で、さまざまな電子製品に触れたことがあるかもしれませんが、その中に含まれる高電圧リチウムイオン電池などの一部のコンポーネントを理解していない可能性があります。次に、小編が皆さんに高電圧リチウムイオン電池の充電方法を学んでもらいましょう。 リチウムイオン電池は、動作電圧が高く、サイズが小さく、重量が軽く、メモリ効果がなく、汚染がなく、放電が少なく、サイクル寿命が長いなどの利点があり、理想的な電源です。 実際の使用においては、より高い放電電圧を得るために、通常、少なくとも 2 つの単一セルのリチウムイオン電池を直列に接続してリチウムイオン電池パックを形成します。
現在、リチウムイオン電池パックはノートパソコン、電動自転車、予備電源などの分野で広く使用されています。 現在、リチウムイオン電池パックの充電は直列充電が一般的に使用されていますが、直列充電方式はシンプルで低コスト、実行も容易であるため重要です。 ただし、単一リチウムイオン電池間の容量、内部抵抗、減衰特性、自己放電の違いにより、リチウムイオン電池パックを充電すると、電池パック内の単一リチウムイオン電池が完全に充電されます。
電気が流れて他の電池が充電されない場合は、充電を継続して充電すると、充電された単一のリチウムイオン電池が充電されることがあります。 また、一部のバッテリー管理システムには均等化機能がありますが、コスト、放熱、信頼性などの理由により、バッテリー管理システムの均等化電流は充電電流よりもはるかに小さいことが多く、均等化効果はあまり良くありません。
当然、一部の単一バッテリーが完全に充電されないケースがありますが、これはリチウムイオンバッテリーパック(たとえば、電気自動車のリチウムイオンバッテリーパック)の場合、大電流になるとさらに顕著になります。 リチウムイオン電池を過度に充電すると、電池の性能に重大な損傷が生じ、爆発して人身事故を引き起こす可能性もあります。 そのため、単一のリチウムイオン電池の過充電を防ぐために、リチウムイオン電池パックには通常、使用中の電池管理システムが装備されています。
管理システムによりリチウムイオン電池ごとの過充電を防止します。 充電時に、単一のリチウムイオン電池の電圧が充電保護電圧に達すると、電池管理システムは直列充電器全体を遮断して充電を停止し、個々の電池が過充電されて他の電池が充電されるのを防ぎます。 リチウムイオン電池は完全に充電できません。
通常、バッテリーメーカーが工場でテストする場合、単一のバッテリーを最初に定電流で充電し、次に定電圧で充電し、最後に定電流で放電して放電容量を測定します。 通常、放電容量は定電流充電容量と定電圧充電容量の合計にほぼ等しくなります。 実際のバッテリーパックの充電プロセスでは、通常、単一のバッテリーに対する定電圧充電プロセスではないため、定電圧充電容量が失われ、バッテリーパックの容量は単一のバッテリーの容量よりも少なくなります。
通常、充電電流が小さいほど、定圧充電容量比が小さくなり、バッテリーパックの容量損失も小さくなります。 そこで、バッテリー管理システムと充電器が連携した直列充電モードが開発されました。 バッテリー管理システムは、バッテリーの性能と状態を最も総合的に把握する装置であるため、バッテリー管理システムと充電機を接続して、充電機にバッテリー情報を理解させ、バッテリーの充電をより効果的に解決します。
いくつか問題があります。 この充電モードでは、バッテリー管理システムの管理および制御機能が働くだけでなく、バッテリーの状態に応じて出力電流を変更し、すべてのバッテリーが充電状態になるのを防ぎます。 バッテリーグループが過充電になり、充電が最適化されます。
バッテリーパックの実際の放電容量も通常の直列充電方式よりも大きくなりますが、この方式では、バッテリーパック内の一部のバッテリー、特にバッテリーパックの数が多い場合、バッテリーの一貫性が悪く、充電電流が比較的高いといういくつかの問題が解決されません。 バッテリーパック内の特定のモノマー電池のいくつかの問題を解決するために、並列充電の組み合わせが開発されました。 しかし、並列充電方式では、各バッテリーごとに複数の低電圧、大電流の充電電源が充電されるため、コストが高く、信頼性が低く、充電効率が低く、接続線が太いなどの問題があります。
ただし、この充電方法では大きな範囲は利用できません。 上記の内容を読むことで、高電圧リチウムイオン電池の充電方法についての予備的な理解が得られ、また、学習の過程でまとめることで、設計レベルを継続的に向上させることができると期待しています。








































































































